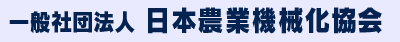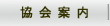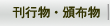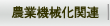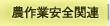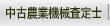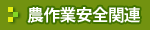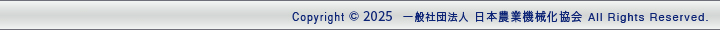●ロボット農機安全コーナー
1.ロボット農機の安全性確保策検討のためのコンソーシアムについて
農林水産省は、平成25年11月にスマート農業の実現に向けた研究会を設立し、ロボット農機やICTの活用による近未来農業について、その実現に向けた検討を行ってきました。中でもロボット農機に関しては安全確保をはじめとしたルール作りについて重点的に検討がなされ、その成果として安全性確保ガイドライン(案)が平成28年度に策定されました。さらに同年、当該ガイドライン(案)の有効性を、実証試験等を通じて検証することを目的に、農林水産省の補助事業「農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討事業」が開始されました。
本コンソーシアムは、ロボット農機に関する安全性の確保に貢献するため、日本農業機械化協会が代表機関となり、研究機関、民間企業等を構成員として組織したもので、平成28年度より当該事業の採択を受け、爾来令和7年度も引き続き事業を実施しています。
2.公表物・参考資料
関係の皆様に向けた安全啓発活動として、ロボット農機の安全に関する資料等を本WEBサイトに掲載します。
1)農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(農林水産省ホームページ)
最終改正:令和6年3月27日
内容:ほ場内やほ場周辺から監視しながら農業機械(ロボット農機)を無人で自動走行させる技術の実用化を見据え、安全性確保のためにメーカーや販売者、導入者、使用者が遵守すべき事項等をまとめたガイドラインです。今回新たに遠隔監視により使用するロボット農機(トラクター、茶園管理機械)に対応する改正が行われました。
2)ガイドライン解説パンフレット(令和7年3月版)
内容:上記ガイドライン(令和6年3月版)の内容を、ロボット農機ユーザーや一般の方々に向けにわかりやすく写真・イラストで説明したパンフレットを作成しました。
3)ロボット農機の安全性確保のための日農工が定めたガイドライン等(一般社団法人日本農業機械工業会ホームページ)
内容:一般社団法人日本農業機械工業会が、ロボット農機利用の際の安全性を確保し、その円滑な普及を図るため、上記ガイドラインに則した業界の指針を決定したものです(農用トラクターをほ場内で自動走行させて農作業を行う場合に適用)。
3.コンソーシアム取組概要
令和7年度
- 令和7年度は、コンソーシアム開始以来のメンバーであった三菱マヒンドラ農機(株)が退会したため、9者構成となった。その他のメンバーは令和6年度と同様の構成である。
- 主な検討内容は、遠隔監視の新たな機種(コンバイン)及びほ場間移動を含む遠隔監視ロボット農機(トラクター及び茶園管理機械)のガイドライン掲載に向けた実証試験・検討である。
令和6年度
- コンソーシアムは、令和5年度と同様に井関農機(株)、(株)クボタ、三菱マヒンドラ農機(株)、ヤンマーアグリ(株)、松元機工(株)及び(株)日本計器鹿児島製作所のメーカー6社に加えて、鹿児島県農業開発総合センター、農研機構農業機械研究部門、秋田県立大学及び日本農業機械化協会(本会)の10者構成で実施した。
- 専門知識を有する学識経験者等で構成する事業検討委員会(委員:18名、専門委員:3名)を設置した。委員会は5回開催し、ほ場間移動を含む遠隔監視ロボット農機の安全性確保ガイドラインに必要な事項、遠隔監視コンバイン等ガイドラインに未掲載の機種についてガイドライン追加掲載に必要な事項等を検討した。また、コンソーシアムが実施した実証試験計画・結果について検討した。
- ほ場間移動を含む遠隔監視ロボット農機(トラクター、茶園管理機械)についてメーカー各社等によって、ほ場間移動を含む自動走行を現地ほ場において実施し技術的課題の抽出・整理につなげた。得られた主な成果は、以下のとおり。
- 道路走行のティーチング・プレイバックにおいてティーチング時とプレイバック時の周囲状況変化への対応に問題があった. また、車速の増加に対して車両の追従遅れにより設定経路からのずれや制動距離が大きくなるなどが明らかになった。
- 遠隔監視端末の視認性は、太陽光、背景色、影等の外的環境に左右されること、前方及び後方左右の3画面を同時に見ることや人・障害物との距離判断が難しいという問題点があった。
- 遠隔監視端末上に監視映像の遅延・停止の状態を確認可能なマーカーを映像に合成して映像の遅延状態を表示することは映像の遅延や停止を確認でき有用であった。ほ場から農道への進入時を想定し、映像、音声、制御信号電送ソフトによって遅延時間を設定して遠隔監視時の視認性を評価した。人の進入では数秒の遅延でリスクとなるが、自動車ではそのリスクが格段に大きくなるので映像遅延を考慮した安全確保策の必要性が明らかになった。
- 遠隔監視端末において音情報では、自車のエンジン音により接近してくる車両や人などを判断することは困難であるが、自動運転開始時のブザー音のアンサーバックや自車のエンジン音を含めた作業音はロボット農機の作業状況の確認に有効であった。
- 茶園管理機械では、GNSSによる枕地(農道)自動走行アプリを遠隔監視自動走行茶園管理機械に付加して、90度旋回、直進、90度旋回、ほ場進入を基本形としてほ場間移動実証を実施した。全天カメラを用いて機体の周囲2.1m以内の死角をなくすよう設定することで、人・障害物を左右は2m以内、後方5m以内、前方50m以内であれば視認可能であった。
- コンバイン等遠隔監視による自動走行のガイドライン未掲載機種について追加掲載を目指して各社で実証試験を行い安全確保策の確認と技術的問題点を検討した。得られた主な成果以下のとおり。
- コンバイン機体の前後左右に取り付けたカメラによる人の認識では、27インチ、7インチのモニターのいずれでも概ね20m以内で認識可能であった。車体の構成上カメラの配置や他のセンサーによる補完が必要と判断された。自動走行開始/再開時の安全確認では15m以内で人を認識可能と判断された。
- コンバインのモニター監視において、実証試験における前後左右のカメラ画像のディスプレイへの配置では、直感でわかりづらいなどの指摘があり、画像配置の検討が必要である。
- コンバインの再起動時の監視カメラによる安全確認では5〜10mの範囲が視認できればよいと判断された。再起動する際の死角の存在については停止前後の録画情報を再生することでカバーできる可能性がある。普通型コンバインでは旋回時にリールを上げた際に視界が遮られることがあった。
- コンバインのモニター監視おいて人の検出結果をバウンダリーボックスで監視画面に表示することで認知精度が向上した。
- 籾の自動排出では、トラックの周囲を確認できる高さでオーガーを一時停止させ、映像で安全を確認したのちに監視者がオーガーを下降させることが望ましい。
- 田植機の湛水条件下での作業において太陽の反射光によりカメラ画像を通した白飛び、黒つぶれの発生メカニズムを解明し、監視カメラを複数設置することでこれらの対策が可能なことを解明した。
- ガイドラインに掲載されている目視監視(6機種)及び遠隔監視(2機種)の全機種について、機種別にガイドライン別表(ハザード整理表)に付加するロボット農機の安全確保に係るリスクと対応策例を、ステークホルダーごとにガイドライン参考資料として取りまとめた。
- 令和6年3月に改正された「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」に関するパンフレット(主として農業者を対象)を制作し、関係機関へ配布した。
令和5年度
- コンソーシアムは、令和4年度と同様、農機及び関連メーカー6社、鹿児島県農業開発総合センター、農研機構農業機械研究部門、秋田県立大学及び日本農業機械化協会(本会)の10者構成で実施した。
- 遠隔監視を含むガイドライン改正素案(令和4年度成果)をベースに現地実証試験方法を提案し、検討委員を含むコンソーシアム関係者に実演、意見交換会を開催した。試験方法はコンソ各社の実証試験に活用されている。
- 構成各社においてそれぞれリスクアセスメントを実施し、それに基づき現地実証試験を実施した。以下に得られた具体的内容を示す。
- 大型モニター(31.5インチ)を用いた監視による障害物の色や走行速度の違いによる視認性や死角の存在などについて検証し、安全性が確認された。
- エッジによる安全性確保がなされていればタブレット端末(10.1インチ)においての遠隔監視は可能と判断した。
- 障害物を検知した際の警告音、パトランプの効果を検証した。
- 現場オペレータと遠隔監視者の両者が自動運転を再開できる場合は、権限の輻輳によるリスクが生じる可能性があった。
- 複数台を同時にモニター監視することは困難でありロボットによるエッジ監視の信頼性確保が重要である。
- トラクター及び茶園管理機械の遠隔監視を含むガイドライン改正案についてコンソーシアム内及び事業検討委員会で検討を重ね、ガイドライン改正案として農林水産省農産局長へ提言した。
- この結果、年度末の令和6年3月27日付で農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの一部改正(農林水産省ホームページ)として公表された。
令和4年度
- コンソーシアムは、令和3年度と同様、農機及び関連メーカー6社、鹿児島県農業開発総合センター、農研機構農業機械研究部門、秋田県立大学及び日本農業機械化協会(本会)の10者構成で実施した。
- 構成各社においてそれぞれ遠隔監視下におけるリスクアセスメントを実施するとともに安全性確保策の有効性等について以下のような実証試験を行った。
- 監視モニターの課題、視聴覚的アラートの効果、複数台監視における非常停止機能等を検討した。
- ほ場間移動において、走行時期による植生や道路わきへの収穫物の一時堆積等により接近検知センサーの誤作動が頻繁に生じることがあり、センサーフュージョンによる安全センサーの信頼性の向上が必要であった。
- トラクター側及び遠隔監視装置側の通信環境・通信システム(LTE単独、LTEボンディング、Local5G等の組合せ)の違いによる映像伝送の遅延や欠落が障害物検知と措置遅延に及ぼす影響を調査した。停止措置がトラクターに届かない場合が生じるケースがあり、遅延のあることをシステムが認識し自動運転を停止する等何らかの対策が必要である。
- 2台のロボットトラクターの遠隔監視中でのイレギュラー挿入、遠隔再起動等の運用場面で監視者のモニターによる監視能力の検証や必要な安全要件の抽出を目的とした複数ロボット農機のリスクアセスメント実証試験方法を検討した。
- コンソ各社のリスクアセスメント・実証試験の結果を踏まえ、ほ場内を自動走行するロボット農機を遠隔監視する場合に現行ガイドラインに規定する目視による監視に加えて必要となる安全確保策や関係者の役割を安全性確保ガイドライン素案として取りまとめた。
- 近々に実用化が期待されるコンバインについてリスクアセスメント及び安全性確保策について実証試験等を行い、ガイドラインへ新たに加える機種として、必要な安全性確保策を農林水産省へ提言した。その結果、令和5年3月29日付ガイドライン改正(ガイドラインの一部改正:農林水産省ホームページ)に反映された。
令和3年度
- 検討対象ロボット農機がトラクター、茶園管理機械に絞られたこと等から、ロボット草刈機メーカー2社、自走式小型汎用台車メーカー2社及び長崎県農林技術開発センターがコンソーシアムから外れ、コンソーシアムは10者構成となった。
- ロボット農機の現場導入の拡大に伴う使用例の増加等から、現行ガイドラインの使用方法に関する規定「ほ場内やほ場周囲から監視する方法」を「ほ場内やほ場周囲等の目視可能な場所から監視する方法」に適用範囲を拡大すること及びロボット農機の作業領域内に立ち入ることができるものについて、現行規定では「使用者、補助作業者」限られるがこれを「使用者、補助作業者、配置の必要な他の農業機械」に拡大することが適当であると提言した。これらの提言は、令和4年3月28日付で(ガイドラインの一部改正(農林水産省ホームページ)に反映された。
- 遠隔監視下における自動走行に対応したガイドラインの制定に向け、当面検討の対象とする機種をトラクター及び茶園管理機械とする新たなガイドラインの構成案を提言した。
- 遠隔監視下におけるロボット農機の完全自動走行に向けた検証及び安全性確保策の検討が現地試験を含めコンソ各社で実施し、自動停止機能のロバスト化、夜間作業を含む遠隔監視映像の視認性調査、遠隔監視におけるアラート、現場作業音声モニタリングの有効性などを検証した。また、通信環境と監視映像の遅延について現地検証を行った。
- ほ場間移動は、農道とその周辺環境により遠隔監視映像に死角が生ずる場合があることを実証した。ほ場から農道への進入、農道走行の現地試験により監視カメラの最適設置場所を検討した。
- ロボット農機の安全性に関する国際規格、諸外国における安全性確保策の制定及び検討状況を調査したところ、諸外国において小型・大型のロボット農機が実際に使用されていること、公道での無人運転の例はないことなどが明らかになった。
令和2年度
- ンソーシアムは、前年度の13者に自走式小型汎用台車メーカーの(株)エムスクエア・ラボ及び(株)DONKEYを加えて15者となった。
- 検討委員会での議論をもとに新たな対象機種として自走式小型汎用台車を加えることや、一時的にモニター等による監視を行う場合に必要な安全確保策などをガイドラインに加えることなどの提言を取りまとめた。その内容は令和3年3月26日付けでガイドラインの一部改正に反映された。
- ロボットコンバインに関して実証試験を含む検討を行い、前年度策定した、「衛星測位情報を利用して自動走行するコンバイン(ロボットコンバイン)に係る危険源及び危険状態に関する整理表及びその対応策例(素案)」を改定した。
令和元年度
- コンソーシアムは、前年度の12者にロボット草刈機メーカーとして(株)筑水キャニコムを加え13者となった。
- 検討委員会での議論をもとに新たな対象機種として田植機、草刈機を加えることなどの提言を取りまとめ、令和2年3月27日付けでのガイドラインの一部改正に反映された。
- 近い将来の実用化が期待されるロボットコンバインについて仮想的なリスクアセスメントを行い、「衛星測位情報を利用して自動走行するコンバイン(ロボットコンバイン)に係る危険源及び危険状態に関する整理表及びその対応策例(素案)」を作成した。
平成30年度
- コンソーシアムは、前年度の8者に長崎県農林技術開発センター、秋田県立大学、(株)日本計器鹿児島製作所及び三陽機器(株)を加え12者となった。
- 前年度の検討機種に加えて、ロボット草刈機及びロボット田植機を新たに検討対象とした。
- 検討委員会での議論をもとに、ガイドライン改訂の必要性を検証した結果、現時点でのガイドラインの改訂の必要性は認められない、とされた。
- 一方、事業で取りまとめたロボット草刈機及びロボット田植機に関する危険源及び危険状態に関する整理表は、今後これらの機種を開発しようとする際の安全チェック事項として有用と考え、公表することとした。
平成29年度
- コンソーシアムは、前年度の6者に鹿児島県農業開発総合センター及び松元機工(株)を加え8者となった。
- ロボットトラクターに加えて茶園管理機を新たに検討対象とし、また、有人監視を更に進めた遠隔監視についても検討対象とした。
- 検討委員会での議論をもとに、提言を取りまとめ、その内容は、平成30年3月27日付けでガイドラインの一部改正に反映された。
平成28年度
- (国)農研機構・革新工学センター、井関農機(株)、(株)クボタ、三菱マヒンドラ農機(株)、ヤンマー(株)及び(一社)日本農業機械化協会の6者が「ロボット技術安全性確保策検討コンソーシアム」を設立した。
- 検討対象機種として、ロボットトラクターを選定した。
- 北海道大学の野口伸教授を座長として、他産業におけるロボット安全の専門家、労働安全の専門家、生産者等を委員とした検討委員会を定期的に開催し、ロボット農機の安全性確保策について様々な角度から議論が行われた。
- 検討委員会での議論をもとに、提言を取りまとめた。その内容は、農林水産省のガイドライン(案)の修正に反映され、平成29年3月31日付け生産局長通知「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」(以下、「ガイドライン」)として公表された。